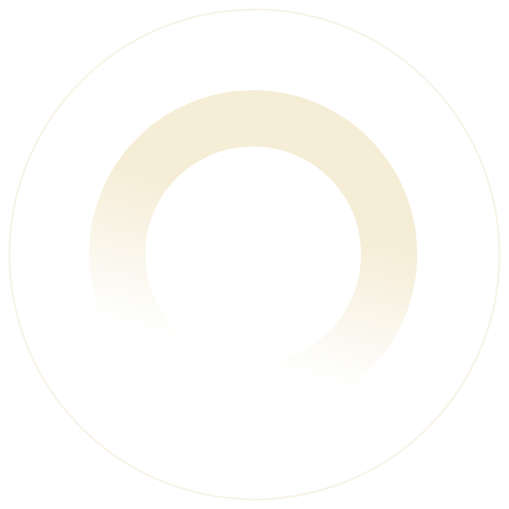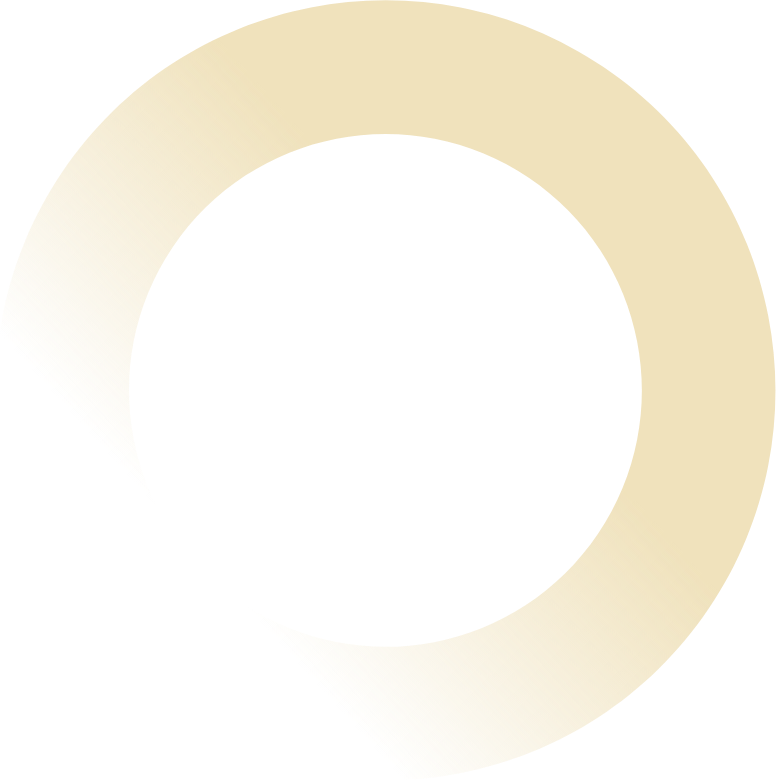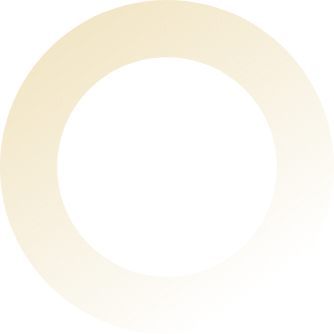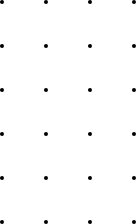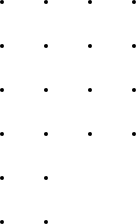目次
1. 介護・保育の採用市場はいま何が起きているのか
10月に複数の現場から上がってきた声として、「応募者の質が明らかに落ちている」という課題があります。ある社会福祉法人の施設長は、次のような実感を示しています。
- 求人媒体やスカウト型サービス経由の応募でも、現場にフィットしない方の比率が増えている
- 人材紹介会社からの紹介でも、短期間での転職回数が多い方や、メンタル面で長期就労の安定性に不安がある方が目立つ
背景には、介護・福祉の採用環境そのものの「売り手市場化」があります。介護職の有効求人倍率(=求職者1人あたりに何件の求人があるかを示す指標)は4倍を超える水準で推移しており、全産業平均(およそ1.2倍前後)と比較すると、採用難が極端な状態にあります。これは特に都市部で顕著で、東海・首都圏・関西エリアでは4倍以上というデータも示されています。一方で地方部は2.5倍前後と差があるため、都市部の施設ほど「とにかく人が来ない」「選べない」という状況が続いています。
こうした超売り手市場では、「応募が来るかどうか」ではなく「定着する人材かどうか」をどう見極めるかが経営課題になります。
つまり今の採用は、単に求人広告費を増やして母集団(応募数)を確保するだけでは限界にきています。応募者のマッチング精度、つまり「この法人で長く・安心して働ける人か」を引き上げる設計が必要です。
2. SNSを本気で運用した保育園で、入園数が過去最高に
一方で、希望のある数字も出ています。ある民間保育園では、Instagramを中心としたSNS発信を本気で取り組み、その結果わずか半年で過去最高となる8名の新規入園(問い合わせ経由の決定ベース)につながりました。入園希望者や保護者のほとんどが「インスタを見て雰囲気が良いと思った」と回答しており、いわゆる“口コミ”の代わりにInstagramが機能していることがわかります。
保育・幼児教育分野では、園の雰囲気・先生の人柄・子どもたちの過ごし方といった「安心感」を、短い動画と写真でわかりやすく伝えられるInstagramが入園検討のきっかけになると言われています。実際に、園の日常、先生のコメント、行事の準備の裏側などをリアルタイムで発信し、保護者と双方向のコミュニケーションを重ねることで、見学予約や問い合わせにつながりやすくなる、という報告も複数出ています。
この保育園では、当社の月次サポートプログラムを継続導入いただいています。
介護・保育の採用でも同じですが、いまの求職者・利用者はまずスマホで調べ、比較し、納得してから動きます。SNSは“たまたま見つける広告”ではなく、“選ばれるための公式リファレンス”に変わってきています。
3. 「理念・ビジョン」を言語化できない組織は、これから本当に採用できない
当社ではいま「ひらめきラボ」という勉強会をテスト的にスタートさせています。月2回、経営者・管理者が集まり、学びを共有し、お互いの取り組みをフィードバックする場です。そこで特に印象に残ったのが、次の指摘です。
このご時世は様々な働き方があり、終身雇用ではない。だからこそ“言葉の力”がより重要。理念・ビジョンを整理しておかないと人はついてこない。
実際、日本型の「ずっとこの会社で働き続ける」という前提は揺らぎつつある、という指摘は各所でなされています。年功序列・終身雇用型の雇用モデルは、企業の人件費負担や経済の成熟化を背景に維持が難しくなっていると言われ、働く人がより自分に合う環境を選び直す時代に入っています。
さらに、リモートワークや柔軟な勤務(例えば「金曜は短時間勤務を許容する」といった運用)が広がり、働き方そのものが分散・多様化しているという報告も増えています。
これは介護・保育業界にも直撃します。かつては「資格を取ったからこの施設でずっと働く」という発想が当たり前でした。しかし今は「この職場の考え方に共感できるか」「私の働き方(時間・負担・役割)に合わせてくれるか」が最優先で、合わなければ辞める・他を選ぶのは当たり前になりました。
だからこそ、求人票やホームページ上で「私たちは何を大切にしている事業所なのか」「どんな仲間と、どんな利用者さんのために、どのようなケア・保育を実現したいのか」を、具体的な言葉で出すことは避けて通れません。抽象的なスローガンでは、もう動きません。
4. 離職率12%→2%まで下げた施設の共通点は“仕組み”
当社が現在調査している特別養護老人ホームでは、この3年ほどで離職率を12%から2%程度まで大幅に改善したという報告がありました。平均的な介護職員の年間離職率は13%前後とされ、近年は過去最低水準まで下がってきているとはいえ、まだ2桁台が一般的です。
その中で「2%」という定着率は全国的に見てもかなり優秀な水準といえます。
特徴は、偶然の成果ではなく“法人としての仕組み”が明確に設計されていることです。たとえば次のような取り組みです。
- 施設の理念として「職員が辞めない特養」を明文化し、日常会話レベルまで落とし込む
- 月1回の面談や状況確認を管理者の仕事としてルール化
- シフトや夜勤負担を個人に押しつけない人員配置
- 柔軟な働き方(短時間勤務・家庭都合の調整など)を当たり前として許容
- 資格取得・スキルアップの支援を行い、権限委譲も進めることで「あなたに任せたい」というメッセージを伝える
- 加算(介護報酬上の評価)を取り切る前提で、給与・処遇を上げ、現場に還元する
ポイントは“優しい”のではなく“組織設計としてやると決めている”ことです。結果として、採用コストを大きくかけなくても辞めない職場ができるということは、採用難の介護・福祉業界では圧倒的な武器になります。
5. 採用は「伴走する時代」へ:11月12日セミナーのご案内
こうした現場の知見を共有するため、11月は積水ホームテクノ様との合同セミナーを開催します。
- 日時:2025年11月12日(水)13:30〜15:30
※13:15〜セッション開始 - 形式:オンライン
- 登壇:積水ホームテクノの佐藤氏(業界での著名講師)、介護経営総合研究所 代表・五十嵐
- 申込:以下より受付中
https://us02web.zoom.us/webinar/register/3017610047201/WN_8sGkm2DMTc-7k166nrSTlQ#/registration
当日の主なテーマは次の3点です。
- 採用の「伴走支援」とは何か
現場と一緒に動き、現場の言葉を求人に反映し、面接から定着フォローまで一気通貫で支える方法と、その成功事例。 - SNS運用による採用力向上
InstagramやLINE公式アカウントなどを活用し、応募前から「この施設、雰囲気いいな」と思ってもらう設計。 - 離職防止プログラムの実際
「辞めない職場」を作るために、理念・ビジョンの言語化、面談などを具体的にお話しします。
まとめ
介護・保育の採用は、もはや「応募が何件きたか」だけでは語れません。
- 応募者の質が落ち、マッチングの見極めが難しくなっている
- SNSが信頼づくりと集客の入口になっている
- 終身雇用ではなく“共感して選ばれる職場”でなければ人は残らない
- 定着率を構造的に高める仕組みを持つ法人だけが、人材確保で優位に立てる
私たちはこれを「採用の伴走支援」と呼んでいます。求人票の作り方だけでなく、理念の言語化から、SNS運用、面接の設計、入職後フォロー、離職防止までを一気通貫で整えること。そのやり方が分かれば、採用コストに依存しない経営に近づけます。
11月12日のセミナーでは、現場で本当に機能した事例を、数字とプロセスでお伝えします。ぜひご参加ください。
専門的なご相談をお受けします
初回相談は無料で承っております。貴施設の現状と課題に応じた最適なプランをご提案いたします。
お問い合わせ: https://kaigo-keiei-labo.jp/contact/
代表プロフィール
介護経営総合研究所 代表 五十嵐太郎
名古屋大学経済学部卒業後、株式会社リクルートにてブライダル市場における営業・マーケティング業務に従事。その後、民間介護企業および社会福祉法人において大規模な経営改善プロジェクトを成功に導く。2021年4月、介護経営総合研究所を創業。
主な改善実績
- 離職率50%削減
- 採用単価30,000円の実現
- 人材紹介・人材派遣費用の完全削減
- 人材紹介会社費用90%削減
- 利益率4倍向上
これらの実績に基づく実践的なコンサルティングにより、介護事業所の持続可能な経営をサポートしています。